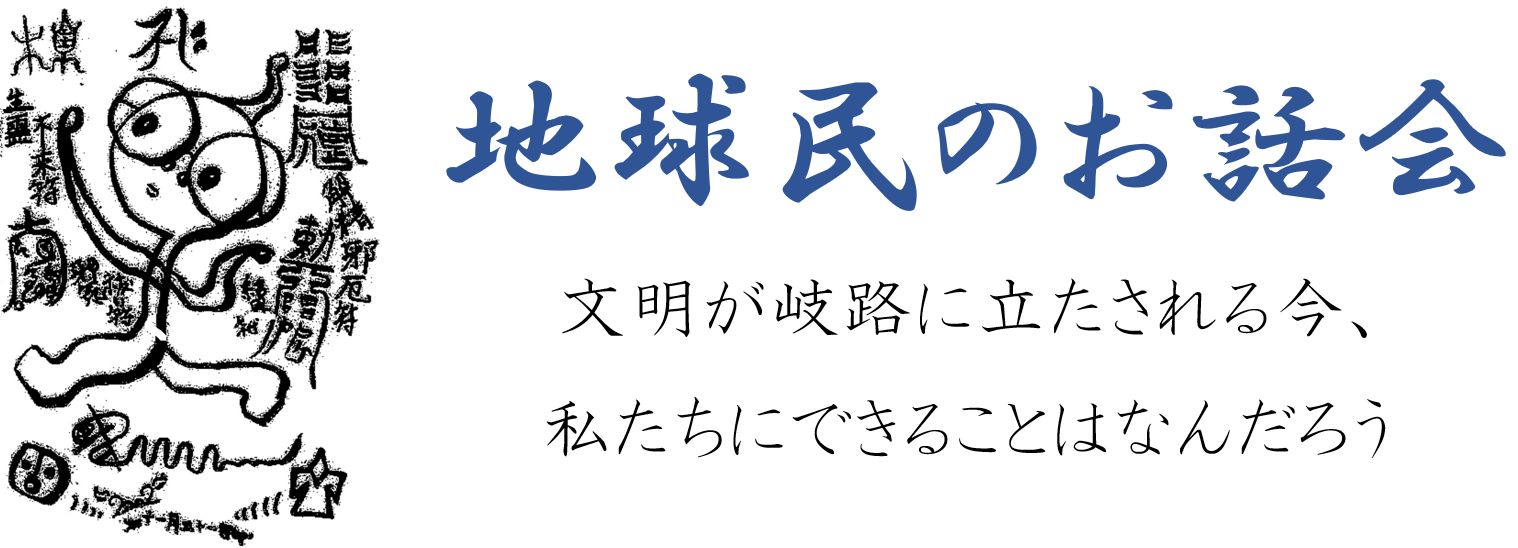描いた絵(掲載した絵)を見ながらの会話。2025年11月25日と日付とともに「月がころがり、重力が増える(強くなる?)」と書いてある。絵は何ものかが降りてきて描いているようで、記憶はないことがほとんどだが、質問を投げかけてみた。人間の進化というテーマは、かなり長期的な視点であることを考慮したい。しかし、時間が加速していることや、この世界の激動の渦中にいると、数年単位でも大きく人間は変化してきていると思う。
これからの人間の進化ー思いの深さとの関係性
月がころがり…
――この絵は、どういうことかわかるかな?
月が(地球に)近づくんじゃないかな。たぶん。
――実は2つの月があって、ひとつが戻ってくると、という予言か何かを読んだ気がする…。
――重力が増えると身体を動かすのが重くなるんじゃないのかな? 月が転がるってことは、今の地球と月と太陽の関係が壊れるってことかな?
――お~い、われわれさん、月が転がるってなあに?
(見えない存在が)笑ってるけど(笑) 。
――月が転がるって、意味不明。
まあ、その時になればわかるんじゃないの。
――天変地異ですか?
天変地異ではなくて、たぶん人間の身体が少しづつ、少しづつ慣れるのか、会話の形が変わるのか。
――この絵を描いたのはいつ?
かなり前かな。2018年のノートに描いてあるからその頃かな?
マイナスから、プラス発信へ
それは進化でしょ。
もしかしたら、病気が重くなるかもしれない、それは想いの深さで。
プラスに思うのか、マイナスに思うのか、人間の中でのね。
なるべくこだわらず、マイナス思考ではなく、マイナス思考が出た時に、否定するのではなく、プラスにしてこれはプラスになった時にどう動けるのか考えたり、言葉にしたりした方がよいと思う。
――この絵に戻ると、2018年に描いて、今からあと2年で2025年になる、というのはいきなり変わるのではなくて…。
ゆっくり徐々に徐々に。
だから地震の場所、氷の解け方、海流の在り方、季節、四季、自転が変わってきているでしょ?
でも徐々に変われば、人間というのは徐々に一緒に変わるわけ。
で、気づいたときに変わっていた、と。
だから、(変化の過程で)いろいろな病気も出てくるし、治るのも出てくるでしょ。
だから、これからは思いの深さと、マイナスから発信しないということは重要になる。
- 1
- 2