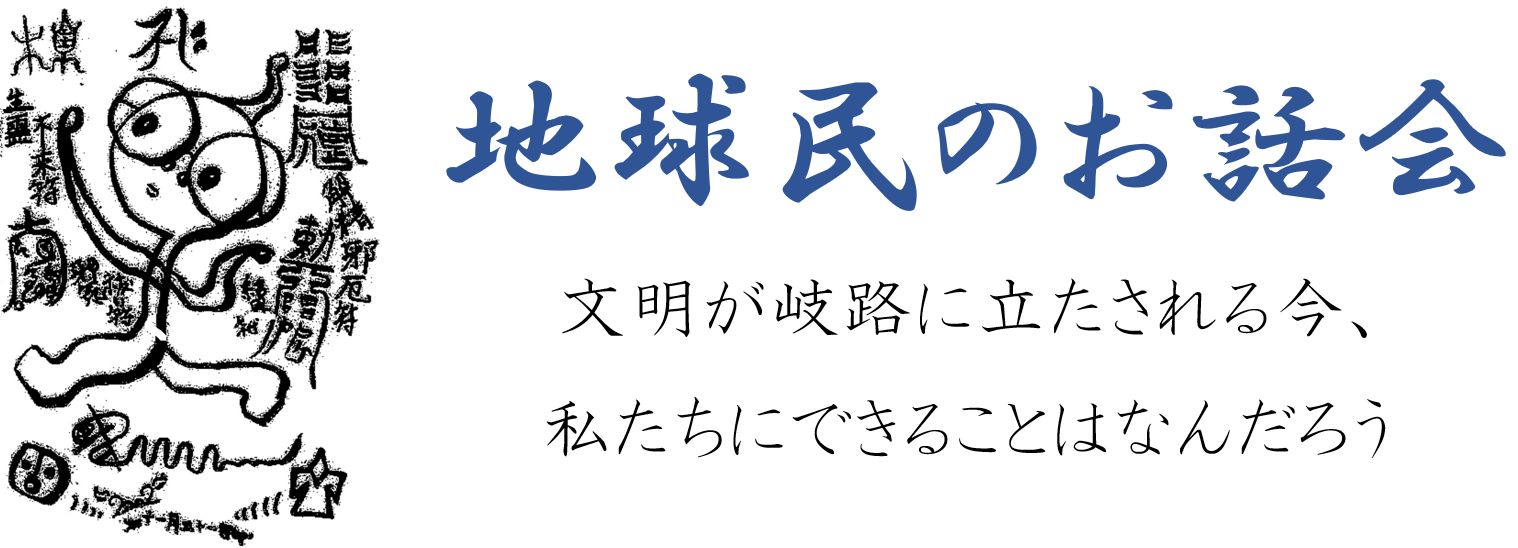「鬼」というと何か怖くて悪い者のイメージがあるが、音を辿ると少しイメージが変わってくる。日本語は異なる漢字でも音が同じであると、共通点があったり、言霊にも通じることがわかってくる。
鬼(おに)と隠(おん)
御皇城山(おみじんやま)の「おみじん(竹ノ内文書に登場する重要な場所)」は「おにじん」だ。「おにじん」は日本人の祖の祖。日本人はもともと鬼だから。
(一方)天とか天子とか天皇、「天」がつくのは「あま」だから。天之日矛とか。矛は守る、攻撃するとか。これは外から(朝鮮半島から?)来たものだ。
(日本人は)みんな鬼の子孫だからね。鬼という響きはいい響きと悪い響きとあるじゃない? 「おに」というのは怖いものではなくて「隠(おん)」、隠すのがうまいもの。「おんりょう」(漢字は不明)といったら、行動を隠しながらする人、忍者ではなく。「隠」とはもともと隠されていた力とか、隠されたものとかの意味だ。
「隠」のものたちは、それぞれ特質によって名前が分かれていた。スサノオの「す」という字、素の人の本質の部分に伝える力、素、魑魅(すだま)の「す」。素直の素。
アマテラスの「アマ」は「天」という字。天(アマ)は「みつめる」とか、「ひろがる」とか。司る人、要するに神の声を聞いて伝える人だ。
スサノオの「ス」
「素」は素直、素になるということ。
―どんな役目の人なの?
その人の素直さを出す人。
―祓いをするときにも「スッ」って払う。
それは元に正すこと。元に戻す、素になるため。ゆがんでいたら、病気、気が病む。病んだところを祓う、開く。「すっ」ていうのは開くんだ。
スサノオとか、スセリヒメ(スサノオの娘、オオナムチ=大国主の妻)とか上に「ス」が付くものはそういう能力がある。祓い、守り。攻撃ではない。
―でも祓って壊れちゃうのもある。
それは相手が弱いんだ。
―音の感じとイメージが合うのが面白いね。そこが日本語の凄いところ。
言葉に乗るもの
「ことたま」と「ことだま」とある。
「おとたま」は、「スッ」とか、「フッ」とか、力を入れると「ハッ!」とか。止めるときは「んっ」とか、「おん」とか低い音だし、これが「おとたま」と言われるもの。
いろんな音が合わさったものが「ことのは」。昔は濁ってなかった。濁点が付くのはそこに止めるというもの。ピンでとめるような。
(このことを)知っていれば自分たちでも使える。人に頼む言葉やお礼を言うときにつかえる。おとたまを知っていれば、ことのはが知らないうちにきれいになる。
―言っている言葉だけでなく、言葉に乗るものがきちんとあり、神につながると思えば汚い言葉はつかえないね。
神は「結び」だからね。
「ふっ」は下に広がる。「腑に落とす」は下がるでしょ。上がる音、下がる音、そこにとどまる音を自分で見つけると面白い。いろんな音がこの世界にある。
―その感覚を忘れてしまっているので思い出さなければ。
好きな音、好ましくない音があるはず。周波数だと思うけど、見つけてみると面白いかもしれないね。
(2015年6月収録 この記事は4年前に掲載した内容のリライトです)
★よりたくさんの方々にこのブログを読んでもらいたいと思っています。記事がご参考になりましたら、以下のクリックもお願いいたします。ブログランキングでは、他にもおもしろいブログに出会えます。